9月の勉強会報告
任意団体ヴィープス(木原一裕チェアマン)は9月18日、千代田区神田錦町のちよだプラットフォームスクウェアで9月度の月例勉強会を開催。会員は複数参加する企業もあり、18人が参加しました。 今回は「ディスカッション ~教えてVieps会員~」と題したセッション。今期から運営委員に就いた平山雄太氏(㈱日本ラベル社長)が企画立案したコンテンツになります。「各社の実際の取り組みや悩んでいることを共有し、会員同士で意見交換・ノウハウ共有をしてみたい」という狙いから、①毎月の営業利益はどう集計していますか②人事評価の仕組み、皆さんどうしていますか、という2題を定めました。

「正解はありません」。司会者は冒頭、会員各位の発言を集約し、何か一つ正しいものを導くことを目的としたセッションではなく「違いを知り、相互に参考になるセオリーやナレッジを持ち帰ることが狙い」であると説明しました。
続いて、平山氏があいさつして企画趣旨に言及。セッション①、自社の売上について「『予算を達成できた』という月はあるものの、後で蓋を開けると『営業利益が思ったほどではなかった』ということがあります。ここの部分について、リアルタイムな集計ができている会員企業がいらっしゃれば伺いたいなといった思いから『皆さんはどう管理していますか』を共有していくことを狙ったディスカッションです」と説明し、まずは当社の事例からと日本ラベルの事例を紹介しました。

日本ラベル(平山社長)の事例と課題
- 受注番号ごとに案件を管理し、資材購入・作業時間を案件単位で記録
- 工場の一人当たりの「分賃」を定め、作業時間に掛け合わせて工賃を算出
- 課題:資材のまとめ買い時に一つの案件にのみ計上してしまい、他案件への振り分けができていない
- 課題:送料の案件ごとの振り分けができていない
- 案件単位での利益の可視化が不十分
その後配布した付せんとペンを使い、参加者が自社の事例を記入していきます。書き終えたらマイクを回し、一人一人発表してくれました。発表後に付せんを回収して一か所に集約、そこから何となくグルーピングを図ってみたい狙いです。 発言の口火を切ってくれたのは、われらが木原チェアマン。製版会社なので印刷会社のような計算式にはなりませんと前置きして、次のように取りまとめました。

フナミズ刃型製版(木原社長・荒井氏)
- 版型はサイズ・色数・形状で価格が決まるため、案件ごとの原価計算は困難
- 人件費の比率が大きく、作業者の技量によって時間が大きく異なる
- オペレーターごとに時間当たりの売上を算出し、月単位で管理 - 個人別の成績開示は反発があり、平均値と目標値を示して月1回のワンオンワンで共有

続いて、運営委員でもある久保井インキの碧木氏もマイクを手に回答しました。
久保井インキ(碧木氏)
- 既製品販売がメーンで定価設定あり
- 特色の受注生産は配合・原料費・工数単価から原価を算出
- 価格決定は碧木氏が全て担当(システム化が課題)
- 配合情報がチャットワークで届き、お客様・数量・配合内容から単価を決定

ラベル印刷会社からは、ULSが経営者、営業責任者、工場長と3者で参加してくれました。(梅垣社長・阿部氏、佐藤氏)
- 作業手配書に工場工賃と営業利益を明記し完全に分離
- オペレーター全員が自分の工賃・原材料費を把握
- 2022年から新システムを導入し、営業全員の考え方・営業会議の質が向上 - 営業と製造で利益の考え方を議論し、各部門の責任者に絶対権限を付与
山王テクノアーツ(山崎氏)
- 工程数が多く手作業が中心のため、作業時間のばらつきが大きい
- 基幹システムで案件別管理が可能だが、入力が不正確になりがち
- 問題がありそうな案件をピックアップして専門担当者が計算 - 全体の数字での利益率算出にとどまる

マキシール(牧社長)
- 送料は一律でお客様から徴収(計算結果を繰り上げて確保)
- まとめ買い商品は1回目に全額お客様に負担してもらい、以降は工賃のみで請求
- キャッシュフローを重視した運用 - 版・型の購買価格と顧客からの予算を洗い出し中

カピタ(柳森社長・長澤氏)
- デジタル機のメーター単価・インク代を厳密に計算すると相場とかけ離れる
- 工業簿記の原価計算(電気代・家賃按分等)を全て入れると現実的でない価格に
- 業界の相場観に沿った見積もりを重視 - 現状は明確な利益管理ができていない
このほかにも、エプソン販売、コニカミノルタ、村田金箔ら各社も申請に発言。「昔のすごく儲かった時代は、多分利益がいくら出てるかなって考えなくても、来た仕事をバンバンやって売上が上がり、絶対儲からないわけがなかった。そういう時代の名残が恐らく、どこの会社にもまだあるのではないでしょうか」(木原チェアマン)など、相互に質問を行うなどして、双方向型で報告と情報の共有を図りました。

続いて、人事評価の仕組みについて。すでに設問①で少し時間も押していたので、付せんに書いてもらった後の発表は、全員ではなく平山社長による指名制としました。当該リポートも同じく押し気味ですので、要点をグッとまとめます。
議題2:人事評価の仕組み
日本ラベル(平山社長)の新しい取り組み
- 以前は営業は売上のみ、生産は機械習熟度・生産高で評価
- 新制度:3つの評価軸(成果・能力・姿勢/態度)を導入
- 上長が目標を明示し、A4一枚のシートで共有
- 目標ごとにウェイト付けを実施
- 新人は姿勢・態度重視、リーダー・マネジメント層は能力・成果重視
- 月1回以上のワンオンワンミーティングで自己評価とフィードバック
- 半期ごとに評価し賞与に反映、年1回で昇給・ポジション変更
- クラス体系:マネージャー、リーダー、エキスパート(部下を持たない専門職)、スタッフ
- 給与レンジを事前公表し、将来設計を立てやすく
- 課題:上長の月次ミーティング負担の軽減

各社の取り組み・意見
フナミズ刃型製版
- 外部コンサル等を経て、最終的に自社でエクセルシートを作成
- レベル別に評価項目を設定(A等級は挨拶等の基本から)
- 業務改善案の提出数を評価項目に含む
- 個人目標設定は困難なため、部署ごとの売上目標を設定
- 部署目標・会社目標・個人評価を掛け合わせて賞与を算出
ULS
- 年功序列を廃止し、貢献度・改善・改革への取り組みを評価
- キャリアに関係なく評価できる項目(挨拶等の当たり前のこと)を重視
- 自己評価が高い社員が多く、自身の弱みを理解していない傾向
- 企業理念・方針の理解度を重視
- 毎週月曜日に社長から企業理念・方針を伝達
マキシール(牧氏)
- 評価シートは他社(谷口シール等)から学んで作成中
- 数値化を進めている段階
- チームプレイを重視し、極端な個人評価は避ける方針
カピタ
- 現状は明確な評価制度なし(「気分」で決定)
- 評価基準:社員が辞表を出しても「しまった」と思わない関係性を維持
- 今後、長澤氏と共に制度構築予定
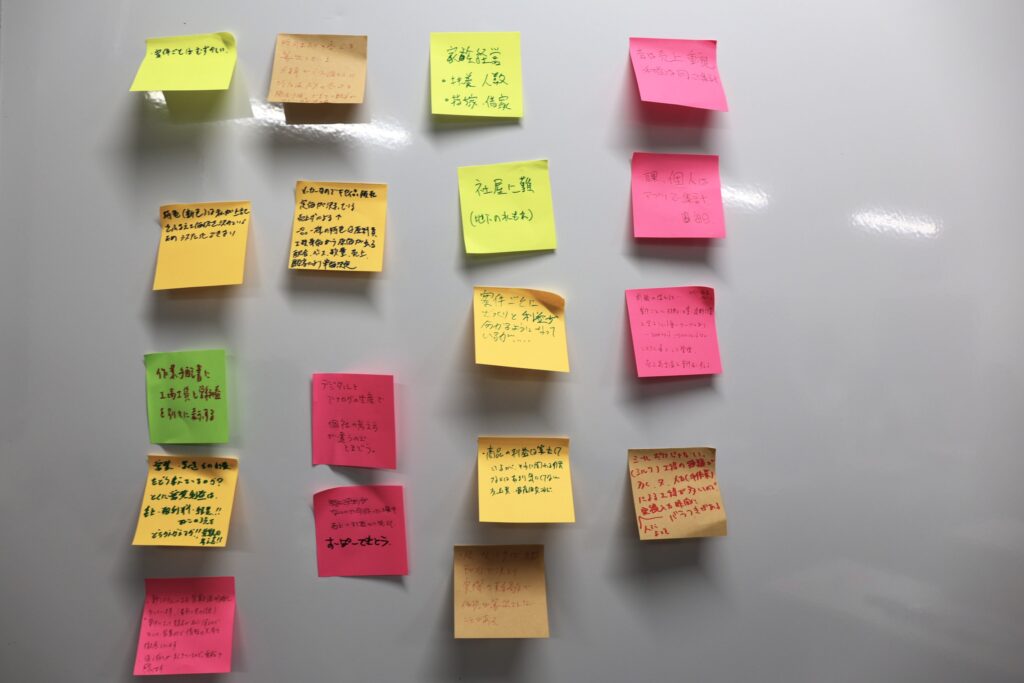
人事評価は、各社永遠の課題でしょうか。中でも、チェアマンの会社は何度もコンサルを入れ替えては挑戦し、それを経て現在は荒井委員が取りまとめた評価シートが完成して運用しているとゴールにたどり着いた様子で「もし興味があればお見せできます」と木原チェアマン。こうしてヴィープス会員同士で忌憚のない情報交換できる場の価値を再確認し、木原チェアマンも「ぜひ第二回もテーマを変えてディスカッションを実施しましょう」と結びました。

平山雄太社長のあいさつ要旨
昨年10月から代表を務めていますが、就任以来社員が楽しく、活気を持って、やりがいを感じながら働ける環境をつくりたいと考えています。
これまでは、昔ながらのやり方を続けてきた部分もあり、それにはよさもありました。ただ、代表が変わることで、社員の間にも「このままでいいのか」「自分は評価されているのか」「昇給はあるのか」といった声が聞こえるようになり、組織としての在り方を見直す必要性を感じています。
私としても、皆の努力にしっかり報いたいという思いがあります。そのためには、報酬の原資となる営業利益を安定的に積み上げる必要があり、利益構造の見直しも重要な課題。今回の議題として、そのあたりの悩みを共有させていただきました。
皆さんの取り組みを拝見し、業態が異なっても共通する課題があること、そして一つの正解がないことをあらためて実感しました。特に「システムで見える化する」という点は、非常に参考になりました。
限られた予算の中で、どうすれば利益を積み上げられる体制を構築できるか。今できる仕組みを見直しながら、少しずつ改善していきたいと考えております。
努力が正当に評価される仕組みを整え、社員が前向きに働ける会社にしていきたい。あらためてそう感じた次第です。 本日はま貴重な機会をいただき、さまざまなご意見を伺えたことに感謝しています。ありがとうございました。


