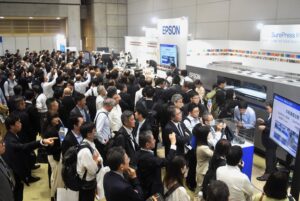11月の勉強会報告
任意団体ヴィープス(木原一裕チェアマン)は11月17日、東京は水道橋駅から至近の貸し会議室で11月度の勉強会を実施しました。
日ごろ使用する文京区の会議室が満室がったため、近い場所でと初めて使用する場所。雑居ビルの3階でしたが、途中の1階2階がキャバクラというアバンギャルドな構造。無事会員が3階までたどり着けるか案じていましたが、どうやら途中の階で休憩する会員はおらず一安心です。
今回のテーマは、ワークショップ形式の「インバスケット的優先順位トレーニング」です。まいばすけっとならほぼ毎日お世話になりますが、このインバスケット(in-basket)とは、まだ処理されていないタスクが入った箱、未処理箱を意味したもの。今日行う「インバスケット研修」とは、指定された特定のシチュエーションや立場のもとで、自分が当事者として制限時間内に未処理のタスクを処理していく演習型の研修。 多くの企業の人材育成において導入されているのだそうです。何だか面白そう。
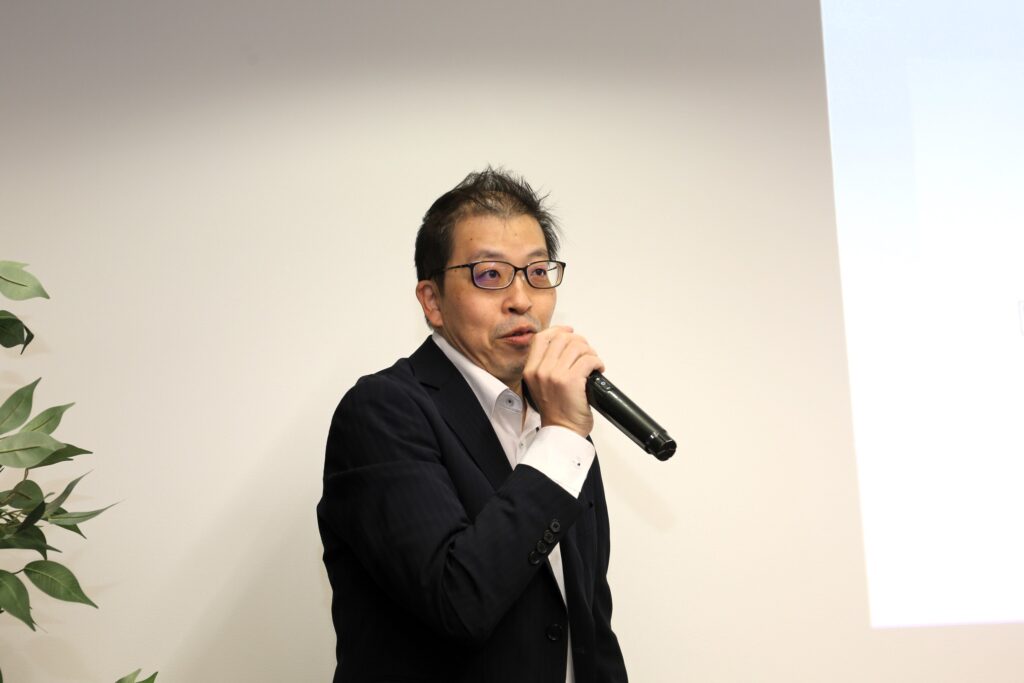
講師をするのは、われわれヴィープスの会員企業であり運営委員会の一人、通称スズケンこと鈴木健二氏(㈱スズパック社長)です。東京グラフィックサービス工業会、東京都正札シール印刷協同組合やその青年部会で要職を務める鈴木氏は、色んなところから情報を仕入れて持ってきてくれます。ためになったワークショップなので、ということで今回実践してくれました。基本的に絶対的な正解がなく、問いごとに定められた設定や条件によってさまざまな解釈ができ、優先順位などを決めて行動を策定していけます。これを繰り返すことで総合的なスキルアアップが図れることから、管理職やリーダーの教育ツールとして活用されています――。こう鈴木氏は説明します。

さらに体系的にまとめると、次のように説明できそうです。
①的確な判断ができる
自身やチームに何が求められているのかを当事者意識を持って考え、洞察力で全体の流れや他の業務との関連性などを把握するこ とで、論理的に意思決定を行うことにつながる
②トラブルの大幅な減少、未然防止
ミスが起きた際に根本的な問題発見をするだけでなく、その問題分析をすることで物事の本質をとらえ、今後のトラブルを回避することにつながる
③組織全体の業務効率が向上する
個々が業務全体を把握し、重要度を考慮して優先順位をつけ処理できるようになることで、結果として組織全体の生産性向上につながる
醸成が期待される効果
①問題発見力②問題分析力③想像力④意思決定力⑤洞察力⑥計画組織力⑦当事者意識➇ヒューマンスキル⑨生産性⑩優先順位設定力⑪優先順位設定力

鈴木氏は特に期待される効果の11番目、優先順位についての重要性に言及します。
「組織の上位職になればなるほど、どの行動から行うべきか判断は難しくなります。 それは、組織の存続に関わったり社会へ重大な影響を与えたりする判断が多くなるからでもあります。 だからこそ、優先順位の設定できるリーダーが求められています」 そういったわけで、鈴木氏は全員に10の例題を配布。タテ軸に「緊急性」、ヨコ軸に「重要性」を置いて〈重要度8・緊急性3〉〈重要度4・緊急性9〉〈重要度・緊急性0〉といった具合に、前提条件をたよりにそれぞれが10題の解を考えました。以下は一部です。
①
■題 名:企画ネーミングについて
■発信者 :部下社員A
■発信日時:4月2日 20:00
■内容:先日ご相談した、例の旅行企画のネーミングですが、どうもよいものが浮かびません。課長からアイデアを出していただけませんか。係長も、課長はアイデアマンだから相談するようにと言われています。
②
■題 名:D観光バス不渡りの件
■発信者 :経理課
■発信日時:4月5日 15:00
■内 容:当社で月間30本ほどの企画で使っているD観光バスが2回目の不渡りを出しました。
③
■題 名:新潟リゾートについて
■発信者 :部下係長B
■発信日時:4月3日 12:00
■内 容:観光庁によると、次世代リゾート地域として新潟が有力候補として挙がっているようです。とはいえ数年先の話ですが。
④
■題 名:アンケート協力依頼
■発信者 :総務課社員A
■発信日時:4月4日 17:00
■内 容:急な依頼で申し訳ありません。実は4月8日期限で各課に総務課のサービス度に関するアンケートをお願いしていたのですが、貴部署には案内が漏れていたようです。お忙しい中申し訳ないですが、期限までに全課員から回答を回収し送ってください。
⑤
■題 名:価格設定について
■発信者 :部下係長C
■発信日時:4月5日 18:00
■内 容:秋の温泉ツアー企画Aの価格ですが、ライバル社の価格情報が手に入りましたので早急にご相談したいのですが、お時間をとっていただけないでしょうか。

筆者のような平社員に対して、幹部、経営者と立場が異なると当然回答も異なります。鈴木氏は複数名を順に指名して、回答と理由を皆で聞いていきました。ある人は「仕事に優先順位なんてつけられないし、例え自分にとって優先順位が低くても相手にとってはそれが10だったりする。だから「心境としては10と10だ」などと殊勝なことをいう人も。(それじゃ仕事にならないしスケジュールも破綻するのでは)と少し感じつつも、いかにもその人らしい考えだと頷けます。ちなみに社内の幹部、社長の直属にあたる人でした。確かに幹部が何人いてどういった業務や役割を分担した組織なのかによっても回答が変わりそうです。

重要度高・緊急性高だと、タテ軸ヨコ軸のマトリクス上では左上にあたりますが、そこに10の回答が集中している人は「すべて優先しなければいけない観念」の傾向だと鈴木氏。「この設定はすべての案件を重視し過ぎているために、多くの案件が左上に集中しています。結局明確な優先順位設定ができていないということになりがちです。これは真面目で 計画的な方に多い傾向です。しなくてもよい仕事もたくさんあるということに気づくことが大切」などとし、右上集中型、中央集中型とそれぞれの特徴と傾向、生じがちな問題を説明しました。
自分の判断が具体的に人とどれくらい異なるのか、なぜ異なるのか。それが可視化できたのはなかなか貴重な体験でした。一度ではさすがに身に付かないので、何度か繰り返し訓練することが大事になりそうです。鈴木講師、ありがとうございました!